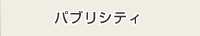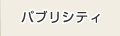- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 高齢者の年金・就労・健康を考える
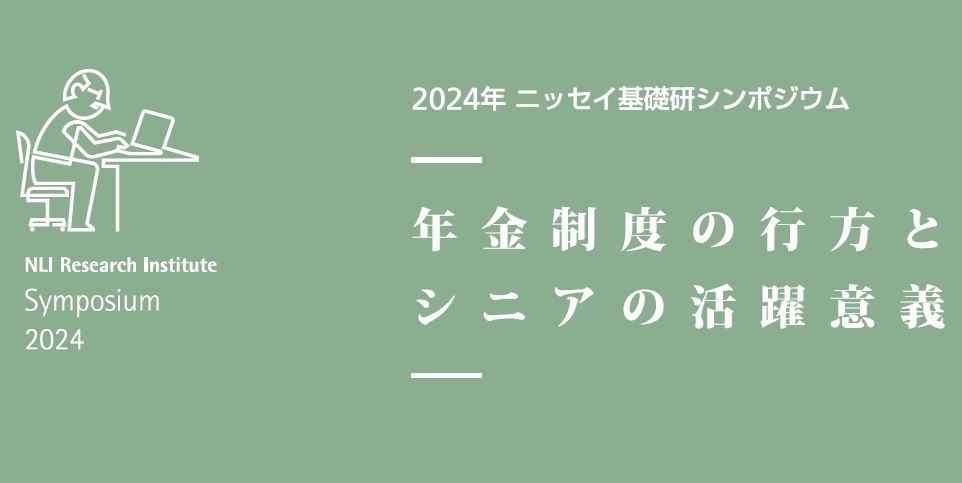
2024年10月22日開催
基調講演
高齢者の年金・就労・健康を考える
| 講師 | 一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏 |
|---|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
3―3. 家族介護の心理的負担
もっと深刻な話をしましょう。それは家族介護の問題です。先ほどのスライドを見ても分かると思いますが、やはり家族介護は大変です。特に長期化すると、家族のメンタルヘルスは非常に大きな影響を受けます。その変化の度合いを決定するのは何かというのを調べてみました。
グラフを見ていただきましょう。これはややこしいことをせず、親の介護が始まってから男性と女性のメンタルヘルスはどのように変化するかを、同じ人をずっと追って調べてみたのですが、上の赤の曲線が女性で、下の青の曲線が男性です。男性の場合、少し低下しているような形になっていますが、統計的にはほぼフラットで、変化なしと考えていただいて構いません。ところが、女性の場合は明らかに悪化傾向が見て取れます。
これをある同僚に見せると、それは男性が女性と違う答え方をしているのだと解説してくれました。男性の場合、「あなたは親の介護をしていますか」という訊き方をすると、〇を付けるのですが、あまりしていないことが多いようです。暇なときにちょっと親の様子を見て、それで、「俺も介護をしているぞ」と言うのですが、女性の介護の関与に比べると非常に浅いことが多いので、あまり当てにしない方がよいということでした。そういうことも含めて見ると、やはり女性の方が介護は大きな負担になることが分かると思います。
ただ、ここで注意したいのは、介護は長期化すること自体がメンタルヘルスの悪化要因になるのか、あるいは介護の仕方が影響するのかという点です。それを調べてみました。
平均的に見ると、女性の場合ですが、5~6年ぐらいの経過を追跡して見てみますと、大体1年ごとにK6のスコアは0.23ほど上がります。そこで、どういう介護の仕方をしているかも統計で分かりますから、介護の仕方を比べてみました。
何に注目するかというと、まず、1日長時間介護をしていますか、具体的には2時間以上やっているかどうかです。やっている人とやっていない人がいるわけです。それから、親御さんがおうちにいるかどうか。施設に入っている、あるいは、きょうだいの家にいて、通いで介護しているかどうかです。それから、介護に専念しているのではなく、パートタイムもそうですが、何か働いているか、あるいは社会参加活動をしているか。それと長時間介護が続いているかどうかという要因の絡み合いです。どちらのほうが、影響があるのでしょうか。介護の長期化が問題なのでしょうか、それとも介護の仕方が問題なのでしょうか。それを調べてみました。
やや面倒な話になりますが、このスライドにある上乗せ効果というところを見てください。これは介護が長期化することに加えて、長時間の介護であればK6スコアの上昇の度合いがどれだけ高まるかを見たものですが、全て統計的に有意になります。長期化そのものの効果は、統計的にそこまで有意ではありません。ですから、介護の仕方こそが介護者のメンタルヘルスを大きく左右するということになります。実は。私も両親がダブルで要介護状態になりまして、妻と手分けをして介護をしていますが、介護の仕方を工夫しないと、介護している方も倒れてしまうということが自分自身の経験からも分かりました。
次に、介護から解放されたらどうなるかということもついでにやってみました。この分析は、あまり先行研究がありません。先行研究があるのは、配偶者が要介護状態から亡くなったというものです。そういうときに残された配偶者のメンタルヘルスはどのように変化するかという研究は諸外国でも結構あります。しかし、介護していた親の要介護状態がなくなった。そのかなりの部分は死亡ですが、それ以外にも施設に行ったとか、あるいはきょうだいで交代したということもあるとは思いますが、その後のメンタルヘルスまでフォローした分析はありません。日本の場合、長期にわたって人々のメンタルヘルスを追跡する統計がありますので、それを見たのがこちらです。
これはK6スコアが5以上の人の比率を見たものですが、介護スタート1年前と比べて、1年後になりますと、男女ともに結構高くなります。それだけメンタルヘルスが悪化するわけです。その後の経過は無視して、介護が終わったらどうかという点だけを見ると、やはり改善するわけです。
これは何を言いたいのかということです。今日は介護の話はあまりしませんが、皆さん、地域包括ケアシステムという言葉をどこかでお聞きになったことがあると思います。介護、医療などを地域全体で支えましょうという仕組みです。これは非常にいい仕組みだと思います。医療と介護が連携して地域の高齢者の面倒を見るというのは非常に重要なことなのですが、その話にはあまり家族が入っていないのです。家族なしでこの仕組みを維持するというのは大変なことだと思います。厚労省のスタンスとしては、できるだけ在宅で介護ケアを維持しようということでしょうが、それ自体はたいへん結構なことだと思います。ずっと自分の住み慣れたところで死ぬまで過ごすというのは、人々の切実な願いなのですが、それを支えるのは家族なのです。その家族のメンタルヘルスについては、政策的にもう少し議論があっていいのではないかと思います。それを申し上げたくて、介護の長期化に応じて、介護に携わっている人たちがどういう状況に置かれるかを申し上げた次第です。
今まで深刻な話ばかりしましたが、では、そういうメンタルヘルスを良い方向にもっていく要因というのはないのでしょうか。
もっと深刻な話をしましょう。それは家族介護の問題です。先ほどのスライドを見ても分かると思いますが、やはり家族介護は大変です。特に長期化すると、家族のメンタルヘルスは非常に大きな影響を受けます。その変化の度合いを決定するのは何かというのを調べてみました。
グラフを見ていただきましょう。これはややこしいことをせず、親の介護が始まってから男性と女性のメンタルヘルスはどのように変化するかを、同じ人をずっと追って調べてみたのですが、上の赤の曲線が女性で、下の青の曲線が男性です。男性の場合、少し低下しているような形になっていますが、統計的にはほぼフラットで、変化なしと考えていただいて構いません。ところが、女性の場合は明らかに悪化傾向が見て取れます。
これをある同僚に見せると、それは男性が女性と違う答え方をしているのだと解説してくれました。男性の場合、「あなたは親の介護をしていますか」という訊き方をすると、〇を付けるのですが、あまりしていないことが多いようです。暇なときにちょっと親の様子を見て、それで、「俺も介護をしているぞ」と言うのですが、女性の介護の関与に比べると非常に浅いことが多いので、あまり当てにしない方がよいということでした。そういうことも含めて見ると、やはり女性の方が介護は大きな負担になることが分かると思います。
ただ、ここで注意したいのは、介護は長期化すること自体がメンタルヘルスの悪化要因になるのか、あるいは介護の仕方が影響するのかという点です。それを調べてみました。
平均的に見ると、女性の場合ですが、5~6年ぐらいの経過を追跡して見てみますと、大体1年ごとにK6のスコアは0.23ほど上がります。そこで、どういう介護の仕方をしているかも統計で分かりますから、介護の仕方を比べてみました。
何に注目するかというと、まず、1日長時間介護をしていますか、具体的には2時間以上やっているかどうかです。やっている人とやっていない人がいるわけです。それから、親御さんがおうちにいるかどうか。施設に入っている、あるいは、きょうだいの家にいて、通いで介護しているかどうかです。それから、介護に専念しているのではなく、パートタイムもそうですが、何か働いているか、あるいは社会参加活動をしているか。それと長時間介護が続いているかどうかという要因の絡み合いです。どちらのほうが、影響があるのでしょうか。介護の長期化が問題なのでしょうか、それとも介護の仕方が問題なのでしょうか。それを調べてみました。
やや面倒な話になりますが、このスライドにある上乗せ効果というところを見てください。これは介護が長期化することに加えて、長時間の介護であればK6スコアの上昇の度合いがどれだけ高まるかを見たものですが、全て統計的に有意になります。長期化そのものの効果は、統計的にそこまで有意ではありません。ですから、介護の仕方こそが介護者のメンタルヘルスを大きく左右するということになります。実は。私も両親がダブルで要介護状態になりまして、妻と手分けをして介護をしていますが、介護の仕方を工夫しないと、介護している方も倒れてしまうということが自分自身の経験からも分かりました。
次に、介護から解放されたらどうなるかということもついでにやってみました。この分析は、あまり先行研究がありません。先行研究があるのは、配偶者が要介護状態から亡くなったというものです。そういうときに残された配偶者のメンタルヘルスはどのように変化するかという研究は諸外国でも結構あります。しかし、介護していた親の要介護状態がなくなった。そのかなりの部分は死亡ですが、それ以外にも施設に行ったとか、あるいはきょうだいで交代したということもあるとは思いますが、その後のメンタルヘルスまでフォローした分析はありません。日本の場合、長期にわたって人々のメンタルヘルスを追跡する統計がありますので、それを見たのがこちらです。
これはK6スコアが5以上の人の比率を見たものですが、介護スタート1年前と比べて、1年後になりますと、男女ともに結構高くなります。それだけメンタルヘルスが悪化するわけです。その後の経過は無視して、介護が終わったらどうかという点だけを見ると、やはり改善するわけです。
これは何を言いたいのかということです。今日は介護の話はあまりしませんが、皆さん、地域包括ケアシステムという言葉をどこかでお聞きになったことがあると思います。介護、医療などを地域全体で支えましょうという仕組みです。これは非常にいい仕組みだと思います。医療と介護が連携して地域の高齢者の面倒を見るというのは非常に重要なことなのですが、その話にはあまり家族が入っていないのです。家族なしでこの仕組みを維持するというのは大変なことだと思います。厚労省のスタンスとしては、できるだけ在宅で介護ケアを維持しようということでしょうが、それ自体はたいへん結構なことだと思います。ずっと自分の住み慣れたところで死ぬまで過ごすというのは、人々の切実な願いなのですが、それを支えるのは家族なのです。その家族のメンタルヘルスについては、政策的にもう少し議論があっていいのではないかと思います。それを申し上げたくて、介護の長期化に応じて、介護に携わっている人たちがどういう状況に置かれるかを申し上げた次第です。
今まで深刻な話ばかりしましたが、では、そういうメンタルヘルスを良い方向にもっていく要因というのはないのでしょうか。
3―4. 社会参加活動の役割
そこで注目したのは、社会参加活動です。これはいろいろな定義がありますが、何らかの形で他人、近所の人でもいいですし、あるいは友人、知人、会社の同僚でもいいです。家族は別にしましょう。家族以外の人たちと一緒に参加する、これが高齢者のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼすのではないかという気がして、これに注目してみました。
一人では駄目です。一番上に趣味・教養と書いてありますが、定年後、おうちにこもってプラモデルを一人で作るというのは、趣味ではありますが、社会参加活動とは言えない。他人とのインタラクション(相互作用)が重要で、何らかの形で他人と関わっているというようなことに注目します。
それから、賃金をもらって働くことは別にしましょう。有給労働も広い意味での社会参加活動ですが、それは別にして、自発的に行っている活動について、メンタルヘルスへの影響を見てみましょう。
これを見ると非常に面白いことが言えます。先ほど家族介護が始まると人々のメンタルヘルスが、特に女性の場合、悪化するという話をしましたが、介護が始まる前に何らかの形で社会参加活動を行っていたか、いないかで、メンタルヘルスの悪化のペースが全然違ってきます。黒い線が社会参加活動を全然行っていなかった人です。赤い線が、何らかの形で少なくとも一つ社会参加活動を行っていた人です。そういう人たちを比較してみました。
もちろん、こういう分析をする場合、介護するから社会参加活動ができなくなったとか、そういう逆の因果関係もきちんと処理しないといけないので、それも統計上処理しています。お見せしているグラフは、その統計上の処理をしていませんが、処理した場合も傾向はそれほど変わりません。何を申し上げたいかというと、世の中と何らかの形でつながりがあると、私たちの老後はリスク要因から解放される度合いが強まるのではないかということです。
それからもう一つは、定年後の状況です。もう皆さんお分かりだと思いますが、私の言葉は関西弁です。私は、実は京都に住んでいます。京都は住民の人たちが参加する活動が結構盛んです。例えば夏休みの終わりごろになると地蔵盆というのがあって、近所の子どもたちを集めて、お地蔵さんの前でお菓子を配ったりするとか、そういう活動が結構しっかりと展開されています。私にも役員が回ってくるわけですが、そういう社会的に活動が活発な地域とそうでない地域で、定年を迎えたときにどういう状況の変化が出てくるか。これは自分自身の問題として分析してみたのです。
社会参加活動が活発な地域と不活発な地域で、定年後の私たちのメンタルヘルスの変化の様子がどのように違ってくるかを見たものです。
すこし見づらいグラフですので注意深く見ていただきたいのですが、これは男性の場合、社会参加活動が活発でない地域で定年を迎えたときにどうなるのを見ています。棒グラフがありますが、ゼロより上に位置しています。先ほど働いていたら、健康にプラスになると言いましたが、その逆で、定年を迎えると、健康面で問題が出てくるという傾向が見られます。それが顕著なのは、活動が不活発な地域です。ところが活発な地域に住んでいると、良くなるか悪くなるか、よく分からないという状況になります。
これは何を意味するかというと、社会参加活動が活発な地域に住んでいると、定年後のメンタルヘルスにプラスの影響が出てくるということです。同じように、日常生活活動に何らかの支障が出てくるという確率は、引退後に少し高まるのですが、活発な地域に住んでいると、統計上、よく分からなくなるということです。
引退して、これで自由な時間ができたということですと、精神的な苦痛を感じる度合いは低くなるわけです。これも、働いたらストレスが高まるという先ほどの話の裏側です。その精神的な苦痛の低くなる度合いは、社会参加活動が活発な地域に住んでいるほどはっきりするということが言えます。
なぜ、こんなことを分析したかというと、社会参加活動というのはかなりの程度、自分からの働きかけですよね。だから、経済学や統計学の用語で言うと、外生変数ではないわけです。自分で決めるような色彩がありますから、その効果の分析は難しいのです。ところが、地域の社会参加活動が活発かそうでないかは、自分から見れば外から与えられたものですから、社会参加活動の重要性が、より明確な形で受け止められるということを意識して、こういう分析をしたわけです。
それでは、どういう理由で地域の社会参加活動の活発な状況が、あなたのメンタルヘルスを良くするのかということです。定年を迎えたときに、住んでいる地域でどんな活動があるか。今までフルタイムで働いていたら、なかなか分からないけれど、定年を迎えると時間が出てきます。そうすると、「私の住んでいる地域ではこんなことをやっているのか。これだったら、私も何かお手伝いできるのではないかな」ということに気が付き、そういう活動をすることになる。そうすると、何か生きがいを感じるなど、プラスの面が出てきて、健康にも望ましい効果が生まれるのではないかと思います。
そこで注目したのは、社会参加活動です。これはいろいろな定義がありますが、何らかの形で他人、近所の人でもいいですし、あるいは友人、知人、会社の同僚でもいいです。家族は別にしましょう。家族以外の人たちと一緒に参加する、これが高齢者のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼすのではないかという気がして、これに注目してみました。
一人では駄目です。一番上に趣味・教養と書いてありますが、定年後、おうちにこもってプラモデルを一人で作るというのは、趣味ではありますが、社会参加活動とは言えない。他人とのインタラクション(相互作用)が重要で、何らかの形で他人と関わっているというようなことに注目します。
それから、賃金をもらって働くことは別にしましょう。有給労働も広い意味での社会参加活動ですが、それは別にして、自発的に行っている活動について、メンタルヘルスへの影響を見てみましょう。
これを見ると非常に面白いことが言えます。先ほど家族介護が始まると人々のメンタルヘルスが、特に女性の場合、悪化するという話をしましたが、介護が始まる前に何らかの形で社会参加活動を行っていたか、いないかで、メンタルヘルスの悪化のペースが全然違ってきます。黒い線が社会参加活動を全然行っていなかった人です。赤い線が、何らかの形で少なくとも一つ社会参加活動を行っていた人です。そういう人たちを比較してみました。
もちろん、こういう分析をする場合、介護するから社会参加活動ができなくなったとか、そういう逆の因果関係もきちんと処理しないといけないので、それも統計上処理しています。お見せしているグラフは、その統計上の処理をしていませんが、処理した場合も傾向はそれほど変わりません。何を申し上げたいかというと、世の中と何らかの形でつながりがあると、私たちの老後はリスク要因から解放される度合いが強まるのではないかということです。
それからもう一つは、定年後の状況です。もう皆さんお分かりだと思いますが、私の言葉は関西弁です。私は、実は京都に住んでいます。京都は住民の人たちが参加する活動が結構盛んです。例えば夏休みの終わりごろになると地蔵盆というのがあって、近所の子どもたちを集めて、お地蔵さんの前でお菓子を配ったりするとか、そういう活動が結構しっかりと展開されています。私にも役員が回ってくるわけですが、そういう社会的に活動が活発な地域とそうでない地域で、定年を迎えたときにどういう状況の変化が出てくるか。これは自分自身の問題として分析してみたのです。
社会参加活動が活発な地域と不活発な地域で、定年後の私たちのメンタルヘルスの変化の様子がどのように違ってくるかを見たものです。
すこし見づらいグラフですので注意深く見ていただきたいのですが、これは男性の場合、社会参加活動が活発でない地域で定年を迎えたときにどうなるのを見ています。棒グラフがありますが、ゼロより上に位置しています。先ほど働いていたら、健康にプラスになると言いましたが、その逆で、定年を迎えると、健康面で問題が出てくるという傾向が見られます。それが顕著なのは、活動が不活発な地域です。ところが活発な地域に住んでいると、良くなるか悪くなるか、よく分からないという状況になります。
これは何を意味するかというと、社会参加活動が活発な地域に住んでいると、定年後のメンタルヘルスにプラスの影響が出てくるということです。同じように、日常生活活動に何らかの支障が出てくるという確率は、引退後に少し高まるのですが、活発な地域に住んでいると、統計上、よく分からなくなるということです。
引退して、これで自由な時間ができたということですと、精神的な苦痛を感じる度合いは低くなるわけです。これも、働いたらストレスが高まるという先ほどの話の裏側です。その精神的な苦痛の低くなる度合いは、社会参加活動が活発な地域に住んでいるほどはっきりするということが言えます。
なぜ、こんなことを分析したかというと、社会参加活動というのはかなりの程度、自分からの働きかけですよね。だから、経済学や統計学の用語で言うと、外生変数ではないわけです。自分で決めるような色彩がありますから、その効果の分析は難しいのです。ところが、地域の社会参加活動が活発かそうでないかは、自分から見れば外から与えられたものですから、社会参加活動の重要性が、より明確な形で受け止められるということを意識して、こういう分析をしたわけです。
それでは、どういう理由で地域の社会参加活動の活発な状況が、あなたのメンタルヘルスを良くするのかということです。定年を迎えたときに、住んでいる地域でどんな活動があるか。今までフルタイムで働いていたら、なかなか分からないけれど、定年を迎えると時間が出てきます。そうすると、「私の住んでいる地域ではこんなことをやっているのか。これだったら、私も何かお手伝いできるのではないかな」ということに気が付き、そういう活動をすることになる。そうすると、何か生きがいを感じるなど、プラスの面が出てきて、健康にも望ましい効果が生まれるのではないかと思います。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る