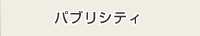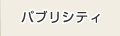- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- パブリシティ >
- イベント(シンポジウム) >
- イベント詳細 >
- 高齢者の年金・就労・健康を考える
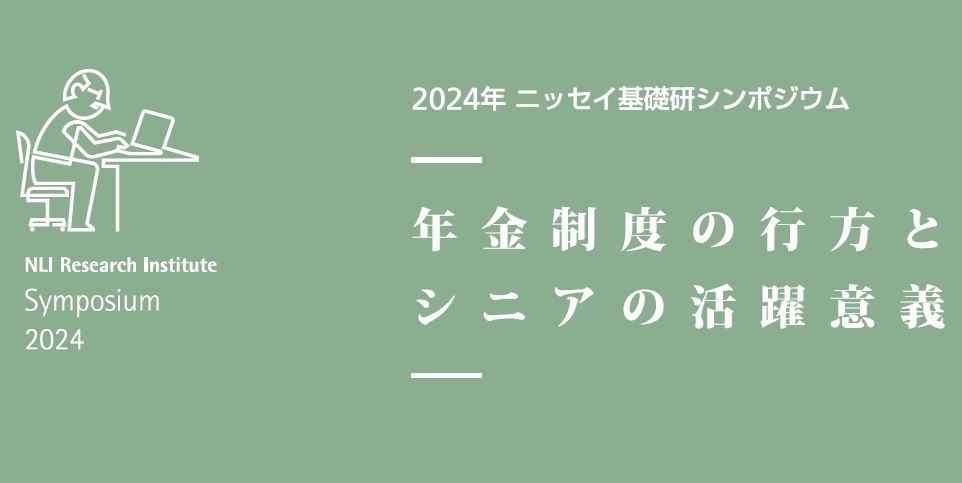
2024年10月22日開催
基調講演
高齢者の年金・就労・健康を考える
| 講師 | 一橋大学経済研究所 特任教授 小塩 隆士氏 |
|---|
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
2―2. 就労が健康に及ぼす影響
次に、別のベクトルを見ましょう。今度は働いたら健康面にどういう影響が出るかを考えます。先ほどは、健康面だけが問題だとしたら、どれだけ働けるかという話をしたのですが、今度は話をひっくり返して、働いたらどれだけ健康になるのかという話をします。
これに関しては、いろいろな先行研究があって、一様な答えは出てきておりません。働くということには結構強制力を伴いますが、それをどのように受け止めるか。ボランティアとか他の社会参加活動とは違う性格を持っていますから、人々の健康に対してマイナスの影響もあるでしょう。どこに分析上の苦労があるかというと、両方とも同時に決まってしまうので、因果関係を抽出するのが面倒な点です。
それを何とかできないかということで、テクニカルな話になりますが、次のような計算をしてみました。2本の方程式を同時に推計するという作業をします。まず働くことによって健康がどれだけ影響を受けるかを1本目の式で推計します。それから、もう1本の式で働き方を推計するのですが、働くことは何によって決まるのかというと、ここでは健康という要因をあえて外します。そこで、何によって決まるのかということで注目するのは年金の仕組みと定年です。非常に荒っぽいのですが、「あなたは年金をもらっていますか」「定年を過ぎましたか」という外から与えられる要因だけで就労が決まると想定します。この2本の方程式を解きます。そうすると、就業が健康にどういう影響を及ぼすのかという一方向だけの因果関係が、荒っぽいですが何とか抽出できます。
実際に出てきた結果は、これです。英語が入って申し訳ありませんが、赤で囲いったところだけを見てください。これは働いたらどうなるかを見たものです。1番目には、Poor Self-rated healthと書いてあります。「あなたは自分で健康状態をどのように評価していますか」という問いに対し、poorです、よくないですと答える確率が低下することが分かります。つまり、働いていると一般的に健康状態が良くなるという傾向が統計的に確認できます。2番目の「自覚症状はありますか」という問いに対しては、これも低めになります。また、ADL(日常生活活動)で訊いているのは、「日常生活を行う上で何か支障がある」というものですが、これも若干マイナスになります。働いていると日常生活もうまく過ごせるということです。
それに対して、次の二つはメンタルヘルス面です。「ストレスを感じますか」とか「心理的に苦痛を感じますか」という問に対しては、プラスになってします。だから「働くと健康にいいですか」という質問があったら、答えるのは難しいですよね。一般的にはいいのだけれど、メンタル面ではちょっとつらいこともあるということになります。
働くと健康面でいいというのはよく分かるのですが、例えば嫌な上司がいるとか、残業させられるということになると、つらいという気持ちになります。そういうのがここに表れているのではないかと思います。
この得られた関係をベースにして、次のようなシミュレーションをしてみましょう。
つまり、「皆さん、70歳まで年金は差し上げません。働いてください。それから定年も、今政府が言っていますが、65歳ではなく70歳まで引き上げます」という制度変更があったときに、皆さんの働き方はどのように変化しますか。それから、それに応じて、健康面でどんな影響が出てきますかをシミュレーションしました。
その結果がこれです。グラフの字が小さくて申し訳ありませんが、上の方は働くことに対してどういう影響が出るかを見ました。青い枠を見てください。これは政策の効果を見たものなのですが、全てプラスになっています。つまり、それだけ年金支給をもう少し先延ばしする、定年も70歳にするということになりますと、皆さんは働き続けます。それはそうでしょう。それでは、健康面でどういう影響が出てくるのかということなのですが、ここでは代表例として、自分の健康が悪いと考える確率がどのように変化するかを見ています。これを見ていただきますと、年齢階層が上にいけばいくほどマイナスがはっきりとしてきます。つまり、それは自分の健康が悪いと答える人が減るということです。これは何を意味するかというと、働いたら、それだけ皆さん健康になれますよということが試算の結果分かります。
同じような作業を他の健康変数についても計算したものをグラフにまとめたものがこちらです。50歳代後半、60歳代前半、60歳代後半について、健康面でどんな影響が出てくるかをそれぞれの変数に注目してまとめました。
一番左にあるのが、自分の健康状態がpoorですと答える人の比率ですが、それが下の方にあります。ということは、健康になりますよということが言えます。それは60歳代後半、つまり、今までは年金をもらって働かなかったが、働くようになりましたという年代ほど影響は大きくなります。それはそうだろうと思います。それから自覚症状も、それを訴える人の比率が低下します。ADLに支障がある人も減るということです。ただ、メンタルヘルスは悪くなるというような結果が出てきます。これは解釈が難しいと思いますが、ここでは定年前と同じような働き方をしてくださいということを想定しているのです。フルタイムならフルタイムで働き続けてください。そうしたらどうなりますかと尋ねています。そうすると、つらいなと思う人が出てくるという結果になっています。
ここで何が言いたいかというと、全体的に見ると、働くということは健康面にプラスの影響が出るでしょうが、精神面ではストレスが出てきます。それを軽減するには、高齢者に今と同じような働き方を強いるのは、無理ではないか。いろいろな働き方を認めた方がいいのではないか。そういうことが、この結果から言えると思います。
以上が、働くということと健康ということの両方の因果関係、どっちがどっちとは言えないのですが、あえて切り離して、どちらかを動かしたら片方がどのようになるかをシミュレーションした結果を申し上げた次第です。
次に、別のベクトルを見ましょう。今度は働いたら健康面にどういう影響が出るかを考えます。先ほどは、健康面だけが問題だとしたら、どれだけ働けるかという話をしたのですが、今度は話をひっくり返して、働いたらどれだけ健康になるのかという話をします。
これに関しては、いろいろな先行研究があって、一様な答えは出てきておりません。働くということには結構強制力を伴いますが、それをどのように受け止めるか。ボランティアとか他の社会参加活動とは違う性格を持っていますから、人々の健康に対してマイナスの影響もあるでしょう。どこに分析上の苦労があるかというと、両方とも同時に決まってしまうので、因果関係を抽出するのが面倒な点です。
それを何とかできないかということで、テクニカルな話になりますが、次のような計算をしてみました。2本の方程式を同時に推計するという作業をします。まず働くことによって健康がどれだけ影響を受けるかを1本目の式で推計します。それから、もう1本の式で働き方を推計するのですが、働くことは何によって決まるのかというと、ここでは健康という要因をあえて外します。そこで、何によって決まるのかということで注目するのは年金の仕組みと定年です。非常に荒っぽいのですが、「あなたは年金をもらっていますか」「定年を過ぎましたか」という外から与えられる要因だけで就労が決まると想定します。この2本の方程式を解きます。そうすると、就業が健康にどういう影響を及ぼすのかという一方向だけの因果関係が、荒っぽいですが何とか抽出できます。
実際に出てきた結果は、これです。英語が入って申し訳ありませんが、赤で囲いったところだけを見てください。これは働いたらどうなるかを見たものです。1番目には、Poor Self-rated healthと書いてあります。「あなたは自分で健康状態をどのように評価していますか」という問いに対し、poorです、よくないですと答える確率が低下することが分かります。つまり、働いていると一般的に健康状態が良くなるという傾向が統計的に確認できます。2番目の「自覚症状はありますか」という問いに対しては、これも低めになります。また、ADL(日常生活活動)で訊いているのは、「日常生活を行う上で何か支障がある」というものですが、これも若干マイナスになります。働いていると日常生活もうまく過ごせるということです。
それに対して、次の二つはメンタルヘルス面です。「ストレスを感じますか」とか「心理的に苦痛を感じますか」という問に対しては、プラスになってします。だから「働くと健康にいいですか」という質問があったら、答えるのは難しいですよね。一般的にはいいのだけれど、メンタル面ではちょっとつらいこともあるということになります。
働くと健康面でいいというのはよく分かるのですが、例えば嫌な上司がいるとか、残業させられるということになると、つらいという気持ちになります。そういうのがここに表れているのではないかと思います。
この得られた関係をベースにして、次のようなシミュレーションをしてみましょう。
つまり、「皆さん、70歳まで年金は差し上げません。働いてください。それから定年も、今政府が言っていますが、65歳ではなく70歳まで引き上げます」という制度変更があったときに、皆さんの働き方はどのように変化しますか。それから、それに応じて、健康面でどんな影響が出てきますかをシミュレーションしました。
その結果がこれです。グラフの字が小さくて申し訳ありませんが、上の方は働くことに対してどういう影響が出るかを見ました。青い枠を見てください。これは政策の効果を見たものなのですが、全てプラスになっています。つまり、それだけ年金支給をもう少し先延ばしする、定年も70歳にするということになりますと、皆さんは働き続けます。それはそうでしょう。それでは、健康面でどういう影響が出てくるのかということなのですが、ここでは代表例として、自分の健康が悪いと考える確率がどのように変化するかを見ています。これを見ていただきますと、年齢階層が上にいけばいくほどマイナスがはっきりとしてきます。つまり、それは自分の健康が悪いと答える人が減るということです。これは何を意味するかというと、働いたら、それだけ皆さん健康になれますよということが試算の結果分かります。
同じような作業を他の健康変数についても計算したものをグラフにまとめたものがこちらです。50歳代後半、60歳代前半、60歳代後半について、健康面でどんな影響が出てくるかをそれぞれの変数に注目してまとめました。
一番左にあるのが、自分の健康状態がpoorですと答える人の比率ですが、それが下の方にあります。ということは、健康になりますよということが言えます。それは60歳代後半、つまり、今までは年金をもらって働かなかったが、働くようになりましたという年代ほど影響は大きくなります。それはそうだろうと思います。それから自覚症状も、それを訴える人の比率が低下します。ADLに支障がある人も減るということです。ただ、メンタルヘルスは悪くなるというような結果が出てきます。これは解釈が難しいと思いますが、ここでは定年前と同じような働き方をしてくださいということを想定しているのです。フルタイムならフルタイムで働き続けてください。そうしたらどうなりますかと尋ねています。そうすると、つらいなと思う人が出てくるという結果になっています。
ここで何が言いたいかというと、全体的に見ると、働くということは健康面にプラスの影響が出るでしょうが、精神面ではストレスが出てきます。それを軽減するには、高齢者に今と同じような働き方を強いるのは、無理ではないか。いろいろな働き方を認めた方がいいのではないか。そういうことが、この結果から言えると思います。
以上が、働くということと健康ということの両方の因果関係、どっちがどっちとは言えないのですが、あえて切り離して、どちらかを動かしたら片方がどのようになるかをシミュレーションした結果を申し上げた次第です。
3――高齢者のライフスタイルとメンタルヘルス
メンタルヘルスの話に移りたいと思います。高齢者は、いろいろなライフイベントに直面します。定年を迎えて引退するのも重要なライフイベントですし、親の介護が始まるのも大変です。場合によっては、配偶者と離婚する、あるいは死別するということもあるでしょう。そのメンタルヘルスがライフスタイルの変化にどういう関係を持っているのかという話をしたいと思います。
3―1. Kessler6スコア
メンタルヘルスには、いろいろな測定の方法があります。政府も公式な統計で結構使っているのですが、Kessler6(K6)というスコアがあります。これを使ってみたいと思います。
どのような質問をするかというと、全部で6つの項目で回答者に〇を付けてもらいます。直訳っぽい言葉なので変な日本語になっていますが、「精神過敏に感じましたか」と聞いて、「いつも」なら1、「まったくない」のなら5というように○を付けてもらうわけです。合計して一番大きい値は30です。30だったら全然問題ないということです。全部1だったら、6ですから一番悪いわけです。そうした合計値を30から差し引きます。そうすると、0から24になります。数字が大きくなればなるほど「あなたは精神的に何らかの問題を抱えています」という尺度になります。これをK6といいます。6というのは、6項目の質問を聞いているからだということです。
では、そのK6はどれくらいなのかということですが、50歳以上の中高年の場合は、このようになります。やはり0の人、全然問題ない人が一番多いのです。でも、3ぐらいが平均です。
この分野の専門家の評価ですが、5以上であれば軽い問題があるでしょう、何か問題を抱えていますねということになります。13以上であれば、「あなた、こんなところでうろうろしていては駄目です。ちゃんとクリニックへ行ってください」というような、結構重症のメンタルヘルスの問題があることになりす。そんなに多くではありませんが、5以上の人は3割ほどいます。皆さんも〇を付けると、私はどこかというのが分かると思いますが、3割ほどの人が何らかの問題を抱えているということです。13以上の重症は3~4%ほどになります。
これを使って中高年のメンタルヘルスを実際に描写するのが、次の作業です。
まず、何か変化が起こったときに、このK6がどれだけ変わるかを見てみたいと思います。もちろん、男女によって結果は大きく違っています。男性の方から見ましょう。もちろん、これはその人のパーソナリティ、学歴、所得など、いろいろな要因によって左右されますので、そういう影響をコントロールした上での話です。
男性の場合のライフイベントで何が問題なのか。ここでは、親の介護、引退・失業、配偶者との離別・死別、それから親との同居が始まることについて調べました。
これは男性の場合ですが、数字は先ほどのK6のスコアがどれだけ上昇するかを見たものです。数字が大きくなればなるほど精神的に苦痛が発生するということを意味します。
これを見ると、親の介護、家族介護が始まると、K6が一番大きく悪化します。
2番目はどうか。「配偶者なし」。これは奥さんと離婚する、あるいは場合によっては死別するというときに、それが大きなリスク要因として働くということです。
ほかにも失業とか親との同居、子どもとの同居、いろいろありますが、やはり男性にとってみれば親の介護が始まるというのは、結構きついイベントです。それから奥さんと別れるというのも大変だということです。
これは男性ですが、女性はどうか。
こちらです。女性も、やはりライフイベントで一番リスク要因なのは、親の介護が始まるということです。これは在宅の場合と施設介護の両方を入れていますが、一番大きいです。
それから2番目は、男性の場合は奥さんと別れることでしたが、女性の場合は、旦那さんと別れるのはどうかというと、下から二つ目なのです。色を薄くしていますが、これは統計的に有意ではないということを意味します。女性の場合は、旦那さんと別れても何ともないというのはまあ分かりますが、それよりもつらいのは、配偶者の母親との同居です。嫁姑問題ですね。今までは核家族が中心で、別々に暮らしていたのですが、お母さんが要介護状態になったので引き取らないといけないと旦那さんが言い出すと、奥さんのメンタルヘルスは急激に悪化することになります。
もう少し長期的なメンタルヘルスの変化が次のテーマです。
メンタルヘルスには、いろいろな測定の方法があります。政府も公式な統計で結構使っているのですが、Kessler6(K6)というスコアがあります。これを使ってみたいと思います。
どのような質問をするかというと、全部で6つの項目で回答者に〇を付けてもらいます。直訳っぽい言葉なので変な日本語になっていますが、「精神過敏に感じましたか」と聞いて、「いつも」なら1、「まったくない」のなら5というように○を付けてもらうわけです。合計して一番大きい値は30です。30だったら全然問題ないということです。全部1だったら、6ですから一番悪いわけです。そうした合計値を30から差し引きます。そうすると、0から24になります。数字が大きくなればなるほど「あなたは精神的に何らかの問題を抱えています」という尺度になります。これをK6といいます。6というのは、6項目の質問を聞いているからだということです。
では、そのK6はどれくらいなのかということですが、50歳以上の中高年の場合は、このようになります。やはり0の人、全然問題ない人が一番多いのです。でも、3ぐらいが平均です。
この分野の専門家の評価ですが、5以上であれば軽い問題があるでしょう、何か問題を抱えていますねということになります。13以上であれば、「あなた、こんなところでうろうろしていては駄目です。ちゃんとクリニックへ行ってください」というような、結構重症のメンタルヘルスの問題があることになりす。そんなに多くではありませんが、5以上の人は3割ほどいます。皆さんも〇を付けると、私はどこかというのが分かると思いますが、3割ほどの人が何らかの問題を抱えているということです。13以上の重症は3~4%ほどになります。
これを使って中高年のメンタルヘルスを実際に描写するのが、次の作業です。
まず、何か変化が起こったときに、このK6がどれだけ変わるかを見てみたいと思います。もちろん、男女によって結果は大きく違っています。男性の方から見ましょう。もちろん、これはその人のパーソナリティ、学歴、所得など、いろいろな要因によって左右されますので、そういう影響をコントロールした上での話です。
男性の場合のライフイベントで何が問題なのか。ここでは、親の介護、引退・失業、配偶者との離別・死別、それから親との同居が始まることについて調べました。
これは男性の場合ですが、数字は先ほどのK6のスコアがどれだけ上昇するかを見たものです。数字が大きくなればなるほど精神的に苦痛が発生するということを意味します。
これを見ると、親の介護、家族介護が始まると、K6が一番大きく悪化します。
2番目はどうか。「配偶者なし」。これは奥さんと離婚する、あるいは場合によっては死別するというときに、それが大きなリスク要因として働くということです。
ほかにも失業とか親との同居、子どもとの同居、いろいろありますが、やはり男性にとってみれば親の介護が始まるというのは、結構きついイベントです。それから奥さんと別れるというのも大変だということです。
これは男性ですが、女性はどうか。
こちらです。女性も、やはりライフイベントで一番リスク要因なのは、親の介護が始まるということです。これは在宅の場合と施設介護の両方を入れていますが、一番大きいです。
それから2番目は、男性の場合は奥さんと別れることでしたが、女性の場合は、旦那さんと別れるのはどうかというと、下から二つ目なのです。色を薄くしていますが、これは統計的に有意ではないということを意味します。女性の場合は、旦那さんと別れても何ともないというのはまあ分かりますが、それよりもつらいのは、配偶者の母親との同居です。嫁姑問題ですね。今までは核家族が中心で、別々に暮らしていたのですが、お母さんが要介護状態になったので引き取らないといけないと旦那さんが言い出すと、奥さんのメンタルヘルスは急激に悪化することになります。
もう少し長期的なメンタルヘルスの変化が次のテーマです。
3―2. 引退夫症候群
まず、旦那さんが引退すると、奥さんにとってはイライラする源以外の何物でもないという話をしたいと思います。
これは先ほどのK6のスコアが、旦那さんが引退する1年前をスタートラインにしてどのように変化したかを見たものです。上に行けば行くほどメンタルヘルスが悪化します。それからバーは95%信頼区間を示したもので、これが下の方が0を上回っていれば、統計的に有意だということを意味します。これを見ると、旦那さんが引退して家にいると、奥さんのメンタルヘルスは悪化しています。今日は男性の方が多いと思うのですが、注意してくださいね。3年、4年たつと、奥さんも慣れて諦めますが、最初の3年ぐらいは結構大変だということになります。
私も先ほどご紹介がありましたように、一橋大学経済研究所特任教授と、特任という二つの文字が入っていましたが、これは給料がぐんと落ちて、授業の負担は変わらないという、皆さんの中にもそういう方がいらっしゃるかもしれませんが、いわゆる役職定年です。今、私の奥さんが一番恐れているのは、来年はまだ特任なのでいいのですが、「それ以降はどうするの。ずっと家にいるんですか」といつも訊かれるわけです。「家にいてパソコンで何か書いて、それでアルバイトできたらいいじゃないか」と言うと、「それは問題の解決にはならない」と言うわけです。家にいるということが、まずいのだと。朝ご飯を食べて、「今日の昼ご飯どうするの」と訊く。それはやめてくれというわけです。昼ご飯を食べたら、「今日の晩ご飯はどうするの」と、それを訊かれるのがつらくて嫌だと。それだったら、どこかへ行ってくれと言うわけです。世間では、働き方改革とか何とか言って、高齢者も働くべきだというではないですか。それはあくまでも建前であって、私は、特に男性の場合、高齢者の就業率を高めないといけない最大の理由は、これは公式な場では言いませんが、奥さんのメンタルヘルスを維持することだと思います。旦那さんはできるだけおうちにいずに外で働いた方がよろしい。
こういう問題を引退夫症候群というのですが、これについてはちゃんとした論文があり、国によって違います。ヨーロッパでも国によって違いますし、中国では、旦那さんが引退すると奥さんはハッピーになるようです。今日午前中にゼミがあったのですが、中国人の留学生に聞いてみたら、やはり定年後、お父さん、お母さんは仲良く過ごしている、楽しく過ごしていると言っていました。ちょっと日本と違うのですね。向こうは共稼ぎですから、男も女も同じ働き方、暮らし方をしているからなのかもしれません。
日本の場合も、夫が引退した奥さんのメンタルヘルスをどういう要因が決定するのか、いろいろ調べてみました。
一つ目は、やはり引退前に奥さんと会話があること。平日は大変かもしれませんが、週末二人でどこかにご飯を食べに行くとかいうふうな夫婦であれば、旦那さんが引退しても問題はそこまでありません。
それから奥さんがボランティア活動をしているとか、町内会の活動をしているとか、そういう社会参加活動をしていると、旦那さんが定年でもそれほど影響はありません。
前の二つは、何となく予想がつきましたが、予想がつかなかったのは三つ目です。奥さんが働いていたらどうかということですが、結果は、奥さんが働いている場合に旦那さんが引退すると、奥さんのメンタルヘルスは悪化します。今までなら、家事は「しょうがないから私がやっていたけれど、あなた、これから会社に行かなくていいんでしょう。ご飯ぐらい作ってくださいよ」と期待しても、「いや、俺はやらないよ」ということであれば、奥さんはイライラするだけです。日本の場合は奥さんが働いていると、引退した旦那さんが家にいると奥さんのメンタルヘルスは悪化しまいます。
これは政策とはあまり関係のないテーマではあるかもしれませんが、引退を契機にして、人々のメンタルヘルスが変わるというお話でした。
まず、旦那さんが引退すると、奥さんにとってはイライラする源以外の何物でもないという話をしたいと思います。
これは先ほどのK6のスコアが、旦那さんが引退する1年前をスタートラインにしてどのように変化したかを見たものです。上に行けば行くほどメンタルヘルスが悪化します。それからバーは95%信頼区間を示したもので、これが下の方が0を上回っていれば、統計的に有意だということを意味します。これを見ると、旦那さんが引退して家にいると、奥さんのメンタルヘルスは悪化しています。今日は男性の方が多いと思うのですが、注意してくださいね。3年、4年たつと、奥さんも慣れて諦めますが、最初の3年ぐらいは結構大変だということになります。
私も先ほどご紹介がありましたように、一橋大学経済研究所特任教授と、特任という二つの文字が入っていましたが、これは給料がぐんと落ちて、授業の負担は変わらないという、皆さんの中にもそういう方がいらっしゃるかもしれませんが、いわゆる役職定年です。今、私の奥さんが一番恐れているのは、来年はまだ特任なのでいいのですが、「それ以降はどうするの。ずっと家にいるんですか」といつも訊かれるわけです。「家にいてパソコンで何か書いて、それでアルバイトできたらいいじゃないか」と言うと、「それは問題の解決にはならない」と言うわけです。家にいるということが、まずいのだと。朝ご飯を食べて、「今日の昼ご飯どうするの」と訊く。それはやめてくれというわけです。昼ご飯を食べたら、「今日の晩ご飯はどうするの」と、それを訊かれるのがつらくて嫌だと。それだったら、どこかへ行ってくれと言うわけです。世間では、働き方改革とか何とか言って、高齢者も働くべきだというではないですか。それはあくまでも建前であって、私は、特に男性の場合、高齢者の就業率を高めないといけない最大の理由は、これは公式な場では言いませんが、奥さんのメンタルヘルスを維持することだと思います。旦那さんはできるだけおうちにいずに外で働いた方がよろしい。
こういう問題を引退夫症候群というのですが、これについてはちゃんとした論文があり、国によって違います。ヨーロッパでも国によって違いますし、中国では、旦那さんが引退すると奥さんはハッピーになるようです。今日午前中にゼミがあったのですが、中国人の留学生に聞いてみたら、やはり定年後、お父さん、お母さんは仲良く過ごしている、楽しく過ごしていると言っていました。ちょっと日本と違うのですね。向こうは共稼ぎですから、男も女も同じ働き方、暮らし方をしているからなのかもしれません。
日本の場合も、夫が引退した奥さんのメンタルヘルスをどういう要因が決定するのか、いろいろ調べてみました。
一つ目は、やはり引退前に奥さんと会話があること。平日は大変かもしれませんが、週末二人でどこかにご飯を食べに行くとかいうふうな夫婦であれば、旦那さんが引退しても問題はそこまでありません。
それから奥さんがボランティア活動をしているとか、町内会の活動をしているとか、そういう社会参加活動をしていると、旦那さんが定年でもそれほど影響はありません。
前の二つは、何となく予想がつきましたが、予想がつかなかったのは三つ目です。奥さんが働いていたらどうかということですが、結果は、奥さんが働いている場合に旦那さんが引退すると、奥さんのメンタルヘルスは悪化します。今までなら、家事は「しょうがないから私がやっていたけれど、あなた、これから会社に行かなくていいんでしょう。ご飯ぐらい作ってくださいよ」と期待しても、「いや、俺はやらないよ」ということであれば、奥さんはイライラするだけです。日本の場合は奥さんが働いていると、引退した旦那さんが家にいると奥さんのメンタルヘルスは悪化しまいます。
これは政策とはあまり関係のないテーマではあるかもしれませんが、引退を契機にして、人々のメンタルヘルスが変わるというお話でした。
コンテンツ紹介
-
レポート
-
受託実績・コンサルティング
【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
ページTopへ戻る