- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- 上期減益の軽視できない重み
コラム
2005年07月19日
1.過去最高を更新する企業収益 7月1日に公表された日銀短観6月調査では、企業の景況感が3期ぶりに改善したが、この背景には過去最高水準を更新する好調な企業収益がある。2004年度の経常利益(全規模・全産業)は、前年度比20.3%と3年連続で二桁の伸びとなった。企業の経常利益計画では、2005年度も前年度比2.7%と伸び率は鈍化するものの、4年連続で増益を確保することが見込まれている。 ただし、年度上期に前年度比▲6.7%といったん減益になった後、下期に同11.4%とV字型の回復を見込んでいる点は気になるところだ。上期の減益については、昨年度までの高い伸びの反動による一時的なものに過ぎないと片付けてしまうことも可能である。しかし、日銀短観6月調査時点で上期減益計画となっていた過去の例を振り返ってみると、厳しい事実に突き当たる。 2.今年度の減益確率は75%? 現行と同様に6月調査(注)で経常利益の年度上期、下期、年度計画が調査されるようになった1984年度以降の例を見ると、6月調査時点で上期計画が減益だったのはこれまでに8回ある。このうち、実際に上期実績が減益となったのは6回、年度を通して減益となったのも6回である。つまり、6月調査時点で年度上期が減益計画だった場合、当年度の実績が減益となる確率は75%と非常に高い。 6月調査時点で上期計画が減益だった8回のうち、(1)前年度実績が減益だったケースが6回(86、87、92、93、94、98年度)、(2)前年度実績が増益だったケースが2回(91、2001年度)である(下表参照)。 (1)のケースでは、そのまま当年度実績が減益となったことが4回と多いが、最終的に増益となったことも2回(87、94年度)ある。この2回はいずれも景気底打ちの時期に当たる。景気回復の初期段階では、企業はなかなか慎重な姿勢を崩さずに弱めの計画を策定する傾向があるが、実際には予想を上回るペースで収益の改善が進み、最終的には増益となったケースである。 一方、(2)のケースでは91、2001年度のいずれも年度実績が減益となっている。前年度が増益の場合、企業はそのまま当年度上期も増益が続くことを見込むこと多い。それにもかかわらず、減益計画になっているということは、企業が年度初めの段階で、すでに前年度までとは違う何らかの変調を認識していたということではないだろうか。いずれの場合も下期の反転により年度では増益を見込んでいたが、実際には企業の期待通りにはならず、最終的に大幅な減益となった。一度方向が変わってしまうと、その流れはそう簡単には止められないということかもしれない。 前年度が増益で、当年度上期の計画が6月調査段階で減益の場合、その年度の実績は減益になる可能性が非常に高いと言える。
3.2001年度のパターンは避けられるか? 今年度の6月調査の結果は、言うまでもなく(2)のケースに当たり、最近では2001年度と同じパターンである。もちろん過去の例が今回も当てはまるとは限らない。また、当時と現在とでは外部環境が大きく異なっており、単純な比較は必ずしも適当ではない。2001年当時は世界的なITバブル崩壊により海外への輸出が急速に落ち込んでいた時期に当たる。現在、輸出は停滞が続いているものの、かろうじて横這い圏内に踏みとどまっている。 しかし、原油価格高騰に伴う原材料費の上昇は、すでに企業収益を圧迫し始めている。企業の計画では、原材料費の伸びは下期には鈍化する見込みとなっているが、原油価格の上昇はいまだ止まっておらず、さらなるコスト増をもたらす恐れもある。また、最近の雇用・所得環境の改善は、個人消費の回復を後押しし、企業の売上増につながるというプラス面がある一方で、人件費増という企業収益の下押し要因となることも事実である。企業の下期V字回復の計画はやや楽観的と考えざるを得ない。 政府、日銀は企業収益について比較的楽観的な見方を示している。直近(7月)の「月例経済報告」、「金融経済月報」では、ともに2005年度の経常利益が4年連続で増益計画となっていることに関する記述は見られるが、上期の減益計画には触れられていない。この点についてはそれほど問題とは考えていないのかもしれない。 しかし、ここで見たように過去の例を参考に考えれば、現時点での上期減益計画はそれなりの重みを持って受け止めるべきで、あまり軽視してよいものとは思われないのである。 (注)現在の短観調査月は3、6、9、12月だが、1996年以前は2、5、8、11月であった。ここでは、1996年以前については5月調査を6月調査に置き換えて考えている。 |
(2005年07月19日「エコノミストの眼」)

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
斎藤 太郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |
| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |
| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【上期減益の軽視できない重み】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
上期減益の軽視できない重みのレポート Topへ

















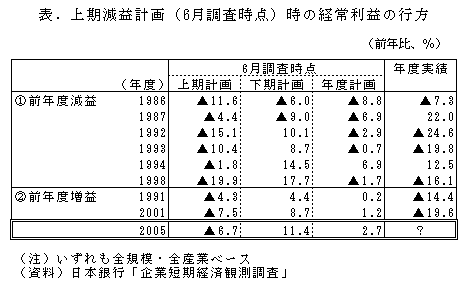

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




