- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 家計の貯蓄・消費・資産 >
- 貯蓄率低下と資本ストックの減少
1.似て非なる「貯蓄率低下」の意味
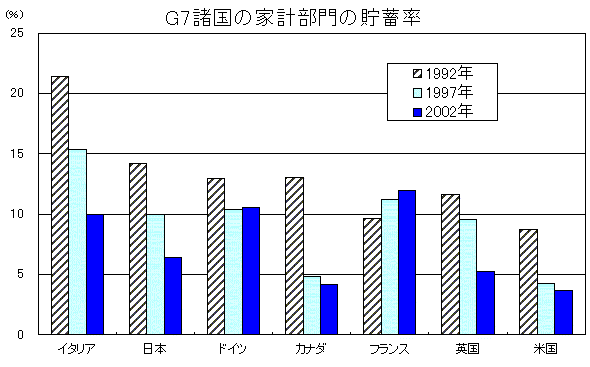
(注)可処分所得(年金基金年金準備金の変動を含む)に対する割合
(資料)内閣府「国民計算計算年報」、OECD「National Accounts」ほか
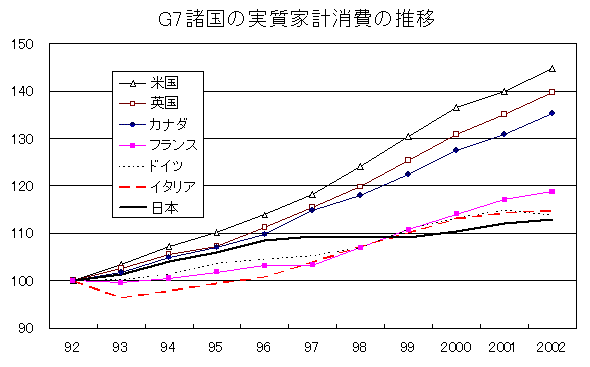
(注)各国の1992年における実質家計消費を100に基準化した指数
(資料)内閣府「国民計算計算年報」OECD「National Accounts」ほか
貯蓄を巡る彼我の差はこれだけにとどまらない。家計、企業、政府のフローの貯蓄を集計した国全体の総貯蓄に関して、最大の低下幅を示しているのが、日本なのである。多くの国において、政府の財政状況は10年前と比べれば、改善された状況にある。つまり、政府貯蓄の源泉である税収が増大しているため、貯蓄率の低下によってフローの家計貯蓄が減少しても、国全体の総貯蓄は従来とさほど変わらない水準が保たれている。日本の場合、事業の再構築に伴って企業の貯蓄は踏みとどまっているものの、政府貯蓄のマイナス幅が拡大しており、国全体の貯蓄水準(フロー)は名目GDP比で大きく低下している。
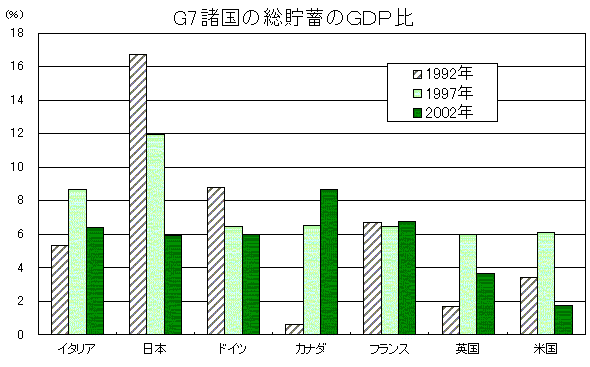
(注)固定資本減耗を控除した純貯蓄(各部門の総計)の名目GDP比
(資料)内閣府「国民計算計算年報」、OECD「National Accounts」
2.投資率低下を背景に資本ストックも減少に転じた日本
数値は統計改訂によって資本ストック増加を示すものに十分に変わり得る範囲のものであり、基調的な減少、反転が見込み難い趨勢とは言えない。しかし、将来の経済活動を供給面から支える資本ストックが、量的には人口と同様にピークに近づきつつある可能性を頭から否定することはできない。
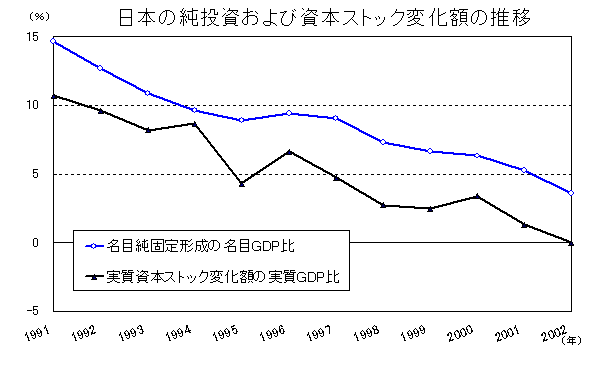
(注)実質資本ストック変化額は期末純固定資産額の前年との差
(資料)内閣府「国民計算計算年報」に基づいて作成
新規投資の原資となるフローの貯蓄に関しても、最初に増強ありきではなく、有益な投資に有効に用いられるよう正しい道筋を付けることが重要であろう。貯蓄とは将来の消費に用いられるためのものであり、どれだけ貯蓄すべきかを決めるのは究極的には投資の収益率になるだろう。もちろん、貯蓄や投資の水準は決して無視できない。それだからこそ、質を加味したえでの量という観点から中身を問うことが今日的課題と言えないだろうか。
(2004年05月10日「エコノミストの眼」)
このレポートの関連カテゴリ
石川 達哉
石川 達哉のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2018/12/28 | 同床異夢の臨時財政対策債-償還費を本当に負担するのは国か、地方か? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
| 2018/07/13 | 「地方財源不足額」は本当に解消されているのか?―先送りされ続ける臨時財政対策債の償還財源確保 | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/08/31 | 再び問われる交付税特会の行方-地方財政の健全性は高まったのか? | 石川 達哉 | 基礎研レポート |
| 2017/07/03 | 増大する地方公共団体の基金残高 その2-実は拡大している積立不足!? | 石川 達哉 | 研究員の眼 |
新着記事
-
2025年11月20日
持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -
2025年11月20日
「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -
2025年11月19日
1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -
2025年11月19日
年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -
2025年11月19日
日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【貯蓄率低下と資本ストックの減少】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
貯蓄率低下と資本ストックの減少のレポート Topへ



















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




