- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 中国経済:大学新卒者は史上最悪の就職難なのに求人倍率は上昇、中国で今起きていること
文字サイズ
- 小
- 中
- 大
1.史上最悪といわれる大学新卒者の就職難
新学期が9月に始まる中国では、新4年生になる前の夏期休暇(7-8月)に新規大学卒業予定者(以下では新卒者と称す)の就職活動が始まるが、6月に大学を卒業して7月から就職することが多い。中国教育部によると、今年中国本土で普通大学を卒業する学生の数は前年比19万人増の699万人となる見込みで、上海市内の新卒者の就職内定率が5月10日時点で44.4%と前年同時期を2ポイント下回るなど今年は史上最悪の就職難といわれている。6月に卒業が決まると、いくつか内定通知を抱える学生が就職先を決断することから、就職内定率は大幅に上昇したと思われる。但し、新卒者が就職できずに就職浪人が増えれば、社会不安の火種ともなりかねないだけに問題は深刻化する。都市部全体の労働需給を見ると決して悪くないものの、大卒者だけの需給を見るとここ数年は求職数が求人数を上回る状況が続いており、雇用にはミスマッチが起きているようだ(図表1)。
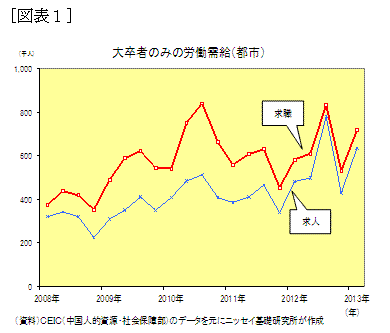
2.雇用ミスマッチの背景にある大学の急増
それでは、中国の労働需給をいくつかの断面から分析してみよう。
まず、男女別に見ると、男女ともに求職数が求人数を上回っており、求人倍率(求人数÷求職数)は男性で0.74倍、女性で0.77倍と1倍を大きく下回るものの、性別不問の求人が多いことを勘案すれば、男女ともに労働需給はやや締まり気味で、性別の問題はないといえるだろう。
次に、年齢別に見ると、25-34歳と35-44歳では求人倍率が1倍を超える労働需給の締まった状況にあるものの、16-24歳と45歳以上では1倍を下回る。しかし、年齢不問を額面どおり受け取れば、年齢別に見ても大きな雇用のミスマッチはなさそうである。
ところが、図表2に示した教育程度別に見ると、高校と修士以上は求人倍率が1倍を超える需給の締まった状況にあるものの、中学以下と大学・大専は1倍を下回っている。学歴不問の求人が多いことを勘案すれば、中学以下の労働需給には大きな問題はないと思われる。
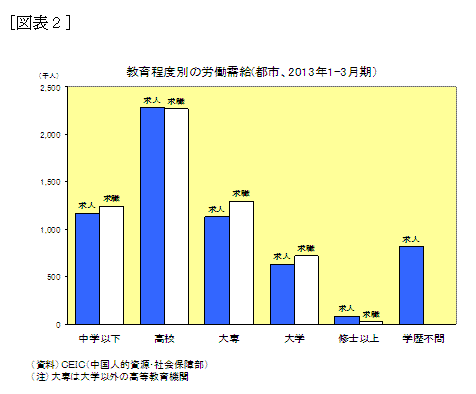
しかし、学歴不問の求人が多くても、大学・大専の学歴を持つ者が喜んで応募するとは考えにくい。大学・大専の学歴を持つ者はその学歴に見合った就職を望むのが自然だからである。大卒者(含む大専)だけに雇用のミスマッチが発生したのは、1998年以来の高等教育改革で大学が急増したことが背景にある(図表3)。
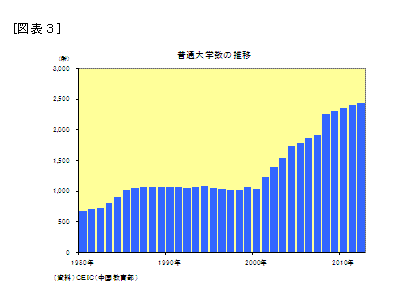
3.痛みを伴う産業構造・各産業内の高度化が重要
大学が急増し大卒者の供給が増えても、大卒者を必要とする仕事が増えれば、大卒者の雇用ミスマッチは起きない。しかし、現状は大卒者を必要とする仕事が十分でなく、雇用ミスマッチが起きている。図表4を見ると、第一次産業から第二次・第三次産業への産業構造の高度化は着実に進んでおり、大卒者を必要とする仕事も右肩上がりで増えている。但し、大卒者の供給はそれ以上のピッチで増加、2000年に約3.6%だった大卒者(含む大専)の割合は2011年には10%弱と2.6倍になった。
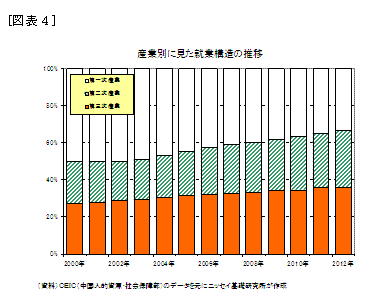
一方、大卒者の雇用ミスマッチは長くは放置できない問題でもある。新卒者は今後も継続的に供給されることから、大卒者の雇用創出を急がないと、就職浪人や高学歴に見合わない仕事に就く大卒者が増えて、社会不安の火種となりかねない。中国共産党が指導する現在の政治体制を今後も維持するには、腐敗汚職、所得格差、環境汚染、社会保障、戸籍、民主化など社会の安定を脅かす諸問題の解決が欠かせないが、大卒者の雇用ミスマッチはその中でも特に重要性が高い。大卒者は一般に知識レベルが高く、諸外国の例を見ても不満が爆発すると政治体制を揺るがすことが多いからだ。
従って、大量の大卒者に十分な雇用機会を提供するため、中国政府は第一次産業から第二次・第三次産業への産業構造の高度化をスピードアップするともに、各産業内の高度化も強力に推進するだろう。
但し、それは既存雇用のリストラという痛みを伴うプロセスでもある。歴史を振り返れば、第11次5ヵ年計画期(2006~2010年)にも過剰生産設備が問題となり淘汰の方針を打ち出した。ところが、リーマンショックで求人倍率が急低下し、その痛みに耐えられなくなった(図表5の○印)。今回は、成長率が低下したにも拘わらず、労働需給全体は締まり気味であり、問題は大卒者の雇用のミスマッチに限られることから、産業構造及び各産業内の高度化を進めるには絶好のチャンスといえるだろう。
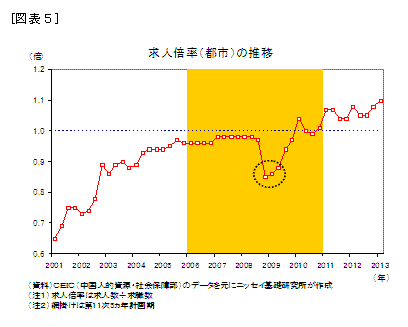
(2013年08月07日「基礎研マンスリー」)
このレポートの関連カテゴリ
三尾 幸吉郎
三尾 幸吉郎のレポート
| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |
| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |
| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |
| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |
新着記事
-
2025年11月04日
今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -
2025年10月31日
交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -
2025年10月31日
ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -
2025年10月31日
2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -
2025年10月31日
保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書
お知らせ
-
2025年07月01日
News Release
-
2025年06月06日
News Release
-
2025年04月02日
News Release
【中国経済:大学新卒者は史上最悪の就職難なのに求人倍率は上昇、中国で今起きていること】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
中国経済:大学新卒者は史上最悪の就職難なのに求人倍率は上昇、中国で今起きていることのレポート Topへ



















 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!




