- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 暮らし >
- 人口動態 >
- 「将来推計人口」の前提と、前提としての「将来推計人口」
コラム
2007年02月05日
| 1.「将来推計人口」と「仮定人口試算」との違い 国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」が昨年末に公表されたが、今度は社会保障審議会の「人口構造の変化に関する特別部会」によって、結婚や子供数に関する国民の希望が実現した場合の将来人口の見通しが提示された。見通しといっても、正式な呼称は「潜在出生率に基づく仮定人口試算」であり、「過去の傾向を将来に投影して作成」される国立社会保障・人口問題研究所の「将来推計人口」とは位置づけが異なるはずである。 そもそも、「潜在出生率に基づく仮定人口試算」を提示した特別部会の目的は「人口構造の変化が社会・経済に与える影響を念頭におきつつ、我が国の社会経済が持続的に発展していくために、どのような論点があるかについて検討を行う」こととされているから、試算値自体よりも、理想的な出生率を具体的にイメージしながら、それを実現するための施策や付随する問題への対処について議論することにこそ意義を求めるべきであろう。 「潜在出生率に基づく仮定人口試算」の拠り所となった「出生動向基本調査」の最新実績値によると、18歳以上34歳以下の男女に関して、生涯のうちに結婚する希望を持つ者と既婚者とを併せた割合は90%を上回るほか、30歳未満の人々が希望する子供数は2人以上であるという。「潜在出生率」とはこれらの希望が満たされた場合の合計特殊出生率のことであり、このうち、希望が完全に実現した場合の合計特殊出生率は最終的には1.75にまで高まるとされている。「将来推計人口」の場合、合計特殊出生率の最終到達水準として想定されているのは、出生高位推計1.55、中位推計1.26、低位推計1.06であるから、「仮定人口試算」の前提となる1.75という「潜在出生率」はかなりハードルが高い目標水準と言える。 もっとも、理想や目標という観点からではなく、「過去の傾向を将来に投影して作成」されている「将来推計人口」に関しても、合計特殊出生率が想定通りの実績値を示してきたかどうかについては別問題である。公的年金制度においては、「将来推計人口」の中位推計が給付と負担の前提数値として用いられており、少なくとも、過去の「将来推計人口」と実績値とを照合し、「高位」「中位」「低位」のうちどの想定に近い推移となったのか、実績値は中位推計の想定からどの程度まで外れ得るのか、認識することは必要であろう。 2.下方改定が続く「将来推計人口」における出生率と死亡率に関する前提 例えば、過去5年間における合計特殊出生率の推移を見ると、その実績値は前回(2002年1月)の「将来推計人口」における中位推計の想定と低位推計の想定のほぼ中間に位置している。しかも、中位推計が想定した将来の最低水準1.31を既に下回って、2005年には1.26に達している。
とはいえ、ほぼ5年毎に改定される「将来推計人口」における中位推計の合計特殊出生率想定を実績値が下回って、新しい推計の際にその想定値が下方改定されるというパターンは、毎回のように繰り返されてきたことである。それどころか、1986年12月推計の「将来推計人口」に関して言えば、低位推計さえも実績値と比べて大きく上方に乖離する想定を採用していたのである。これを機に、中位推計や低位推計において合計特殊出生率がすぐに反転上昇するような想定は採用されなくなり、1992年9月推計以降は、次回の推計が実施される時点で実績値が低位推計の想定を下回ってしまうという事態はなくなった。 しかし、次々回の推計が実施された時点で比較すると、1997年1月推計における低位推計が想定した合計特殊出生率の最終到達水準を実績値が既に下回っているのである。現在の公的年金制度は、今後100年間の収支が安定することを要件として、給付と負担の設計を行うことが求められており、その前提として用いられる将来人口の予測値は100年という歳月に耐えられる「賞味期限」の長いものであることが望ましい。その点では、そこで用いられている2002年1月実施の「将来推計人口」は、今後も前提としてそのまま利用し続けることができるほどの「賞味期限」を持っているかどうは疑問である。 「将来推計人口」の前提に関しては、死亡率についても同様のことが当てはまる。各年齢における死亡率の積算によって算出される平均寿命に関して、「将来推計人口」公表時の想定とその後の実績値とを比較すると、実績値が想定を上回る展開が続いている。そのため、新しい推計の度に前提となる死亡率も下方改定が行われている。
3.見直しが避けられない公的年金の給付と負担 出生率と死亡率の下方改定によって、今回の「将来推計人口」では、前回の推計結果と比べて、人口減少のペースが加速する一方、65歳以上人口の割合がピークに達する時期は後ずれし、その水準は高まることが予測されている。特に、前回の中位推計の結果からは、「2050年頃までは人口減少と高齢化が同時進行」、「2050年以降も人口減少は持続するが、高齢化の進行は一段落」と言えたが、今回の出生中位推計に基づく限り、高齢化の進行が一段落するのは2050年よりも20年以上も後になる見込みである。
ここで、新しい出生中位・死亡中位推計に基づいて給付と負担の試算を行うならば、保険料率を改定せずに0.9%より高いスライド調整率を適用すれば、現役世代の賃金の50%という給付水準を確保することはできなくなるはずであり、50%という水準を確保しようとすれば、2017年度以降の厚生年金料率を18%に固定することはできなくなるはずである。金利や賃金上昇率の仮定を変えない限り、給付削減と保険料引き上げの両方をなしで済ませることは不可能である。そして、「将来推計人口」の前提となる出生率や死亡率が下方改定される度に、同様の問題は繰り返し起こるはずである。 これまでのように、最新の情報を反映した蓋然性の高い「将来推計人口」を5年毎に策定し直すことや、その改定された「将来推計人口」における中位推計に基づいて、公的年金の給付と負担に関する試算を新規に実施することは、もちろん重要である。代替的試算として、低位推計に基づく給付と負担の見通しを提示していることも評価できることである。 しかし、今後100年間に対して、過去の「将来推計人口」は、低位推計でさえも出生数の下限シナリオには程遠いものであったことも事実である。公的年金制度の設計に際しては、より厳しい前提や推計結果にも目を向けるべきであろう。そうした観点に立つと、「将来推計人口」の次に登場したのが、「潜在出生率に基づく仮定人口試算」のみというのは、社会的なバランスがとれていない感じがする。「将来推計人口」における出生低位推計よりも低い出生率仮定に対応した将来人口の計算もあって然るべきであるし、それに基づいた給付と負担に関する見通しを代替的試算として提示することも必要ではないだろうか。少なくとも、公的年金の給付と負担に関する楽観的な見通しを提示するために、「潜在出生率に基づく仮定人口試算」を「悪用」することなどはあってほしくないものである。 |
石川 達哉
研究・専門分野
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年04月18日
「新築マンション価格指数」でみる東京23区のマンション市場動向【2023年】(1)~東京23区の新築マンション価格は前年比9%上昇。資産性を重視する傾向が強まり、都心は+13%上昇、タワーマンションは+12%上昇 -
2024年04月17日
IMF世界経済見通し-24年の見通しをやや上方修正 -
2024年04月17日
不透明感が高まる米国産LNG(液化天然ガス)輸入 -
2024年04月17日
英国雇用関連統計(24年3月)-失業率は増加し、雇用者数も減少 -
2024年04月17日
米住宅着工・許可件数(24年3月)-着工件数は23年8月以来の水準に低下、市場予想を大幅に下回る
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
-
2023年07月03日
News Release
【「将来推計人口」の前提と、前提としての「将来推計人口」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
「将来推計人口」の前提と、前提としての「将来推計人口」のレポート Topへ


















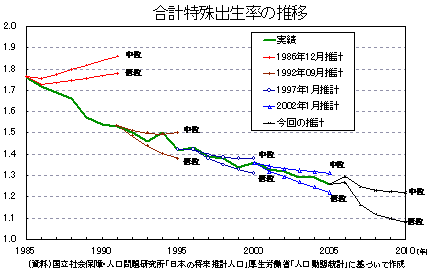
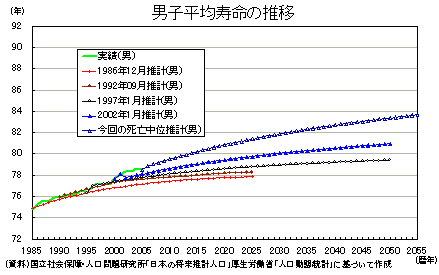
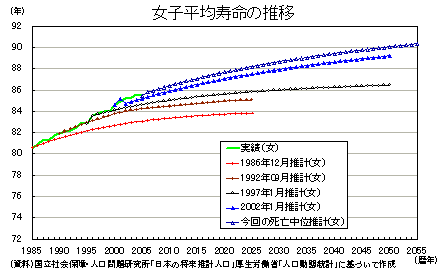
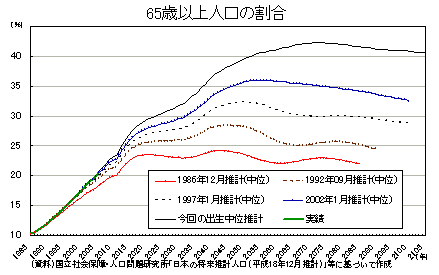

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!





