- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >
- 経済 >
- 日本経済 >
- 「GDPギャップ」過信の危うさ
コラム
2006年07月24日
| 1. 注目されるGDPギャップ デフレ脱却がいよいよ現実のものとなりつつある中、経済全体の供給力と総需要との乖離を表す「GDPギャップ(=需給ギャップ)」の注目度が高まっている。 内閣府は、デフレ脱却の判断基準のひとつとしてGDPギャップを挙げているが、今年の「経済財政白書」では、GDPギャップが2005年10-12月期に約8年ぶりにプラスに転じたという試算を示した。また、日銀は7月の金融経済月報で、マクロ的な需給ギャップが需要超過状態に入っているとの判断をもとに、景気判断を前月までの「着実に回復」から「緩やかに拡大」に変更した。 GDPギャップは、物価変動圧力を見るための重要な指標のひとつであり、最近のGDPギャップの動きからは、日本経済の潜在的な供給力を実際の需要が持続的に上回ることにより、物価上昇圧力が徐々に高まっていることが読み取れる。ただし、GDPギャップはあくまでも推計値であり、その数字はかなりの幅をもって見るべき性質のものである。それにもかかわらずGDPギャップのプラス転化が、あたかも絶対的な真実であるかのように伝えられている現状には少なからず違和感を覚える。 2. 推計方法、推計時期によって異なるGDPギャップ GDPギャップ=(現実のGDP-潜在GDP)/潜在GDPで表される。このうち、現実のGDPは内閣府の公表データによって知ることができるが、潜在GDPは直接観察することができないため、推計によって求められる。推計方法、推計に用いるデータ等が違えば、潜在GDPの推計結果も変わり、そこから計算されるGDPギャップも変わってくる。 潜在GDPの概念にも大きく分けて2通りの考え方がある。ひとつは、労働、資本をフル稼働させた場合のGDP(=最大概念の潜在GDP)、もうひとつは労働、資本が過去の平均的な稼動状態にある時のGDP(=平均概念の潜在GDP)である。最大概念の潜在GDPを使うと、GDPギャップは常にマイナスの値をとるのに対し、平均概念の潜在GDPを使うと、労働、資本が平均的な稼動状態にあるときにGDPギャップはゼロとなり、それよりも稼働率が高ければプラス、低ければマイナスとなる。 日銀はこの春、潜在GDPの再推計を行ったが、その際に潜在GDPの概念をそれまでの「最大概念」に基づくものから、国際的に主流となっている「平均概念」に基づくものに変更した。日銀が潜在GDPの概念を変更した背景には、GDPギャップがマイナスのままでゼロ金利を解除するというのは説得力に欠けるという判断も働いたものと思われる。 ここで、内閣府推計のGDPギャップ(06年7月公表「経済財政白書」による)と日銀推計のGDPギャップ(06年5月公表の日銀レビュー「GDPギャップと潜在成長率の新推計」による)の動きを比べてみよう。 下図から分かる通り、「バブル崩壊以降、ほぼ一貫してマイナスを続けてきたGDPギャップが、足もとでは若干のプラスに転じている」という大きな流れは両者とも変わらない。しかし、より詳細に見てみると、99年頃、01年末から02年初にかけて、内閣府推計のGDPギャップは4%を超えるマイナスとなっていたのに対し、日銀推計のGDPギャップは3%前後とマイナス幅が小さくなっている。また、今回の回復局面において、GDPギャップがプラスに転じた時期は、日銀推計値の2005年4-6月期に対し、内閣府推計値ではそれより2四半期遅い2005年10-12月期となっている。これは、日銀と内閣府で潜在GDPの推計方法がかなり違っているためである。 また、推計を行った時期の違いによってもGDPギャップは変わってくる。5年前の平成13年度版経済財政白書(01年4-6月期まで推計)と今年の経済財政白書を比べると、推計方法は基本的に同じであるにもかかわらず、四半期毎の動きがかなり異なっており、プラスとマイナスの符号が異なる期も散見される。5年前はGDP統計が1995年基準であり、GDPの実質化の手法が固定基準年方式だった(現在は2000年基準、連鎖方式)ため、当時と現在では実質GDPの計数自体が大きく変わっていることが主な理由である。
結局、GDPギャップというのは、様々な要因によって大きく振れる性質のものであり、その水準や短期的な動きにあまり振り回されることは賢明とは言えないだろう。足もとでGDPギャップがプラスになったとは言っても、その水準はたかだか1%にも満たないものであり、データの改定などに伴い再推計を行えば、事後的にマイナスになることも十分ありうる大きさである。日銀、内閣府とも推計結果を示す際には、潜在GDPやGDPギャップの推計結果は十分な幅を持って見る必要があるという注を付けている。しかし、新聞報道等でGDPギャップの数字が伝えられる際には、このような注意書きは省略されることが多いため、GDPギャップ推計の限界は必ずしも正確に伝えられていないのではないだろうか。 日銀がGDPギャップを景気判断の重要指標として前面に押し出すようになったことは、ある意味では英断とも言える。しかし、その一方で不確実性の高いデータをもとに景気判断を行うことには、ある種の危うさも感じる。 今回のゼロ金利解除は、日銀が推計するGDPギャップがプラスとなる中で行われたため、両者(金融政策の方向とGDPギャップの符号)は整合的なものであった。しかし、将来的には両者の方向が必ずしも一致するとは限らず、たとえばGDPギャップがプラスの領域にあったとしても景気が悪化していて利下げが必要であるという局面もありうるだろう。そうした時に、GDPギャップにあまりに大きな意味を持たせてしまうことが、機動的な金融政策運営の妨げになりかねない、というのは考え過ぎだろうか。 |

03-3512-1836
経歴
- ・ 1992年:日本生命保険相互会社
・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ
・ 2019年8月より現職
・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)
・ 2018年~ 統計委員会専門委員
公式SNSアカウント
新着レポートを随時お届け!日々の情報収集にぜひご活用ください。
新着記事
-
2024年04月23日
他国との再保険の監督に関する留意事項の検討(欧州)-EIOPAの声明 -
2024年04月23日
気候変動-温暖化の情報提示-気候変動問題の科学の専門家は“ドラマが少ない方向に誤る?” -
2024年04月23日
今後お金をかけたいもの・金融資産 -
2024年04月23日
今週のレポート・コラムまとめ【4/16-4/22発行分】 -
2024年04月22日
2024年3月、グローバル株式市場は上昇が継続
レポート紹介
-
研究領域
-
経済
-
金融・為替
-
資産運用・資産形成
-
年金
-
社会保障制度
-
保険
-
不動産
-
経営・ビジネス
-
暮らし
-
ジェロントロジー(高齢社会総合研究)
-
医療・介護・健康・ヘルスケア
-
政策提言
-
-
注目テーマ・キーワード
-
統計・指標・重要イベント
-
媒体
- アクセスランキング
お知らせ
-
2024年04月02日
News Release
-
2024年02月19日
News Release
-
2023年07月03日
News Release
【「GDPギャップ」過信の危うさ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。
「GDPギャップ」過信の危うさのレポート Topへ

















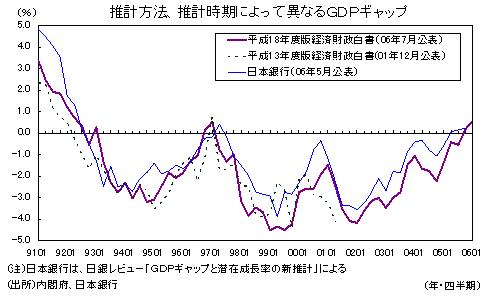

 各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!
各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!





